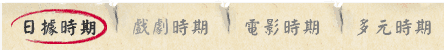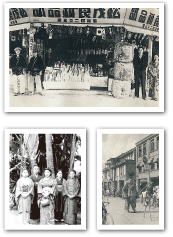
臺北市文獻委員會提供
日本統治時代初期の台北では、万華や大稲埕に商業活動が集中していました。馬関条約(下関条約)締結後、日本による占領統治が始まると、町は有無を言わさず改造され、台北の城壁も取り壊されて近代的な道路や用水路が整備され、統治者の権威を象徴する新しい建物が建造されました。この頃の西門町は来台した日本人の居住区となり、紅楼の八角堂と十字楼は日系移民の新しい生活を支える商店街でした。日本文化が入り込むにつれて、紅楼は故郷を懐かしむ日本人の買物天国となり、当時の台湾人にとっては最新の流行発信地となりました。
1908年に落成した紅楼の階上には食堂が16軒あり、階下では洋雑貨や菓子、玩具、文具、化粧品、靴、洋傘などが売られ、いずれも日本人が経営する高級品店でした。十字楼内では青果や肉類などの食料品を扱っていました。長年ここで出店していた黄蔡玉鑾女史のお話では、蔡家が青果や雑貨を販売していた当時、日本人は一切値切らないので、商売繁盛、大もうけしたそうです。最盛期には、5坪ほどの店で主人と店員7人が生活するだけの売り上げがあったそうです。
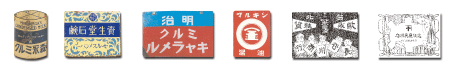

一中學(今建國中學)
台北市文獻委員會提供

1912年啟建至1924年竣工
,整體風格仿文藝復興式
風格,為近藤十郎風格鮮
明的作品之一。
臺北市文獻委員會提供
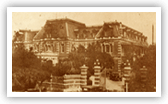
越百貨站前店,是松崎萬
長代表作之一,1908年與
紅樓同年落成,外觀相當
豪華,1945年在美軍密集
轟炸時損毀。
台北市文獻委員會提供
台灣書籍文獻均見西門紅樓(原稱西門市場八角堂)設計者為時任職於台灣總督府官房營繕課的近藤十郎。近年日本建築師松崎萬長之後人來臺拜訪台灣古蹟學者李乾朗、學者黃俊銘及曾任職日據時代協志營造廠的廖欽福先生的後代,試圖舉證說明,西門市場之建築為其先人與近藤十郎所共同設計。
近藤十郎師事英籍建築師Josiah Conder,於1906年抵臺任職於總督府官房營繕課,並於1907年負責設計台北西門市場及彩票局,同時期也可能設計大稻埕市場及台灣日日新報社。1910年設計第一中學(今建國中學);1911年設計基隆郵局;1916年設計台大醫院舊館,是其巔峰之作。松崎萬長(1858~1921)為留學德國之建築師,日本建築學會創立者之一,在臺任職於總督府鐵道部,重要作品有基隆車站、鐵道飯店、新竹車站等,皆獲很高評價。但日據初期在臺灣的日人建築師以追隨英國風格為主流,故松崎萬長的記載多有所忽略。依日本建築學會所發表的專刊特別指出:「西門市場的八角形狀是近藤十郎的作品中少見的簡潔、粗獷豪邁具決斷力的設計,正是松崎萬長特有的手法。」
 |
 |
 |
第一賣店設立。 黃永銓提供 |
西門市場外觀落成。 謝明書提供 |
西門市場外觀。 萬華區公所提供 |